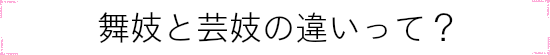
舞妓と芸妓の違い
まずは、そもそも舞妓と芸妓って何?どう違うの?という方は実は多いと思います。舞妓体験をするので、少しだけ、舞妓と芸妓のお勉強をしましょう!
舞妓の起源
祇園には八坂神社という有名な神社仏閣があります。そこへたくさんの人がお参りに来るようになりました。そのお参りに来る人達の為にお茶屋さんができました。今では有名な「二軒茶屋」(「柏屋」と「藤屋」という2軒のお茶屋、現在では「柏屋」のみが健在)が最初と言われています。お茶屋さんはやがて繁盛して大きくなります。最初はお茶や和菓子を置いていましたが、やがて料理を振舞うようになり、お参りにくる人を楽しませようとお茶を出していた女の人が三味線を弾いたり、舞を踊りだすようになります。これが舞妓の起源と言われています。
 舞妓
舞妓
年齢/15才~20才ぐらい
期間/4年~5年ぐらい
お仕事/京都のお店で舞を振舞ったりお酌をし、お客さんを楽しませる。
衣装の特徴/花簪、可愛いお着物、だらり帯、おこぼ
舞妓は芸妓になるための見習いの期間となります。舞妓は4年~5年ぐらいで「私、大人になりました!と宣言する【衿かえ】」という儀式で芸妓へとなります。
 芸妓
芸妓
年齢/20才ぐらい~引退するまで
期間/衿かえの儀式終了後~引退するまで
お仕事/京都のお店で舞を振舞ったりお酌をし、お客さんを楽しませる。
衣装/べっ甲櫛、大人っぽい着物、締め帯、草履
芸妓は舞妓よりも芸が磨かれ、豊富な知識、洗礼した話し方、女性としての魅力が必要になります。芸妓は引退するまではずっと芸妓でいることもできます。引退すると、屋形(置屋/会社)のおかあさん(経営者)になったり、飲食店のお店を出したり、結婚したりと芸妓によって様々です。
花街って?
現在、京都には、6つの花町があります。
祇園甲部、祇園東、上七軒、先斗町、宮川町、島原の6つです。
現在は島原を除く、5つの花町が残り、実際に花町として賑わっています。
現在、この5つの花町を「五花街」と呼ぶようになっております。
祇園甲部、祇園東、上七軒、先斗町は
八坂神社から四条大橋辺りに集中しており、
上七軒のみ北野天満宮付近にあり、少し離れています。
もうすでに花街ではない、島原はJR丹波駅に近いところにありました。
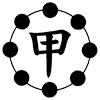
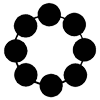
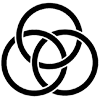
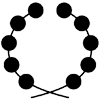
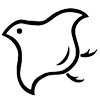
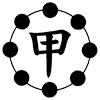
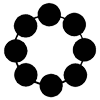 祇園甲部・祇園東
祇園甲部・祇園東
五花街の中でも最大の規模であるのが祇園甲部です。
現在はお食事処などに舞妓が呼ばれるようになりましたが、
最初の起源はお茶屋(以下、水茶屋)でした。
水茶屋が祇園界隈に始めて許可されたのが、寛文五年(1665年)です。
四条河原の東側に新しく、川端町、仲之町、弁天町、二十一間町、常盤町、東石垣町の六町が開け、祇園新地なり、京都最大の歓楽街となった。
歌舞伎などの芝居もので大いに賑わい、とても人が集まったといわれる。
これが現在の祇園甲部である。
また、それから後、1732年(享保17年)には八代将軍吉宗が茶屋株を公許し、
富永町、末吉町、清本町、新橋通の元吉町、橋本町、林下町等の
祇園新地内六町に茶屋町が造られた。
これが、今の祇園東にあたり、この付近には現在、「富美代」「房の家」「みの家」「丸八」などの有名なお茶屋があります。
現在、祇園甲部や祇園東は歴史的建物が多くあり、今も舞妓が練り歩く。
そんな優雅な情景がいまだに残り、たくさんの観光客で賑わっています。
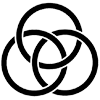 宮川町
宮川町
1666年に宮川町ができ、1670年に護岸工事の石積みが完成したため、
この宮川町に急速に町並みが整いました。
1751年にお茶屋の営業許可が下り、
この地域には、出雲大社の女性巫女「阿国(おくに)」が京都で念仏踊りを踊り、
その後、阿国の歌舞伎踊りが盛んになりました。
この宮川町に、南側に3座、北側に2座、
大和大路に2座の計7座の櫓(やぐら)が公許、とても踊り盛んな花街でした。
しかし、江戸幕府が女歌舞伎を禁止、それに変わって、「若衆歌舞伎」となり、
現在、歌舞伎は男性だけが舞台に立つという歴史背景があります。
現在は観光客は少なくなっており、優雅に散策できるようなところになってます。
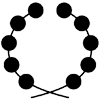 上七軒(かみしちけん)
上七軒(かみしちけん)
上七軒は実は、最古の花街なのです。
15世紀中ごろ、室町時代に将軍足利義政の時代に北野社、
今日の北ノ天満宮が一部焼失し、
神社の修造作業中に、残った材料を払い下げてもらって、
7軒のお茶屋が建った。これが上七軒の起源なのです。
豊臣秀吉と縁が深く、よく大茶会というお茶会を催した。
その際、この上七軒が休憩所となった。
このことから、お茶屋としての営業権が認められ、花街として発展しました。
上七軒の芸妓は少し特殊で、北野天満宮の巫女が、少し年齢を重ねると、
巫女の職を離れないといけないため、占いをしたり、お茶たて女となった。
このお茶たて女が上七軒の芸妓の起源といわれている。
この上七軒は昔、お茶屋、商家、織屋などが混在する町でした。
今ではお店の数はめっきり減ったものの、
面影は残っており、北野天満宮のあとに上七軒を歩く観光客も多い。
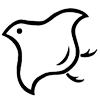 先斗町(ぽんとちょう)
先斗町(ぽんとちょう)
先斗町は三条から四条を鴨川に沿って南北に500m続く細長い地区です。
先斗町とう名前はいくつか言われがあり、ポルトガル語のポント(先、先端、点、場所などの意味)に由来しているというのが一般的です。
天文12年(1543年)、初めてポルトガル人が種子島に漂着して依頼、日本が鎖国するまでに、ポルトガルやスペインと交流があり、ポルトガル人がたくさんいたため、ポルトガル語が使用されたのではないかと言われています。
1670年に石垣が作られ、土砂を入れ、中ノ島となりました。
ここに家が並び始めたのが、先斗町です。
1674年に5軒程、家ができ、そこから急速に町並みが整えられました。
1712年には、料理屋の営業許可が下り、お茶屋が多くできました。
先斗町には、「白人(由来は素人)」と呼ばれる公的ではない遊女が多く見受けられた。
その後1813年に芸妓の取り扱いの許可が下り、
芸舞妓が行き来する花街となっていきました。
先斗町以外の花街では、「祇園育ち」の芸妓をそろえるのがブランドだったが、
先斗町のみ、全国の花街から芸達者なものを募り、受け入れていました。
現在では、レストランやスナックが多く、食事をするなら先斗町というイメージだが、現在も芸妓・舞妓が行き来する花街なのです。
島原
島原は、日本最古の公許遊郭でした。
島原の花街は現在なく、面影を残す家がわずかに残っているだけです。
ここは遊郭であり、太夫(花魁)が多く所属し、とても華やかな街でした。
島原の歴史を振り返ってみると、最初に遊郭を許したのが豊臣秀吉であり、
最初は柳町二条遊郭を始め、それが現在の島原に移ったといわれています。
八坂神社から離れた島原は徐々に衰退し、1854年の夏の大火によって消失。
島原はこうしてなくなっていってしまいました。
現在では、角屋と輪違屋の2軒の揚屋(お茶屋)が残っている。
角屋は国の重要文化財となり、博物館になっている。
ラブ舞妓体験~舞妓体験口コミサイト~について
「ラブ舞妓体験」舞妓体験徹底解析口コミサイトです。舞妓体験ってたくさんありますよね?舞妓変身は皆様にとって初めてな人も多いはずです!そこで、舞妓体験処の口コミサイトを立ち上げてみました!当サイトは京都で人気の舞妓体験の楽しさと舞妓になったときの喜びをみんなで共有し、共感できるような口コミサイトです。舞妓体験した後の観光なども考え、いろんな京都のスポットの口コミ紹介していきます。また、舞妓体験のお店探しのお手伝いも兼ねておりますので、お店の感想や体験談の口コミなども掲載しております。 LOVE@管理人


